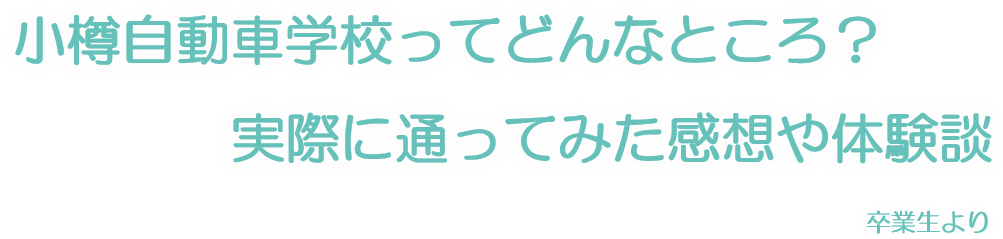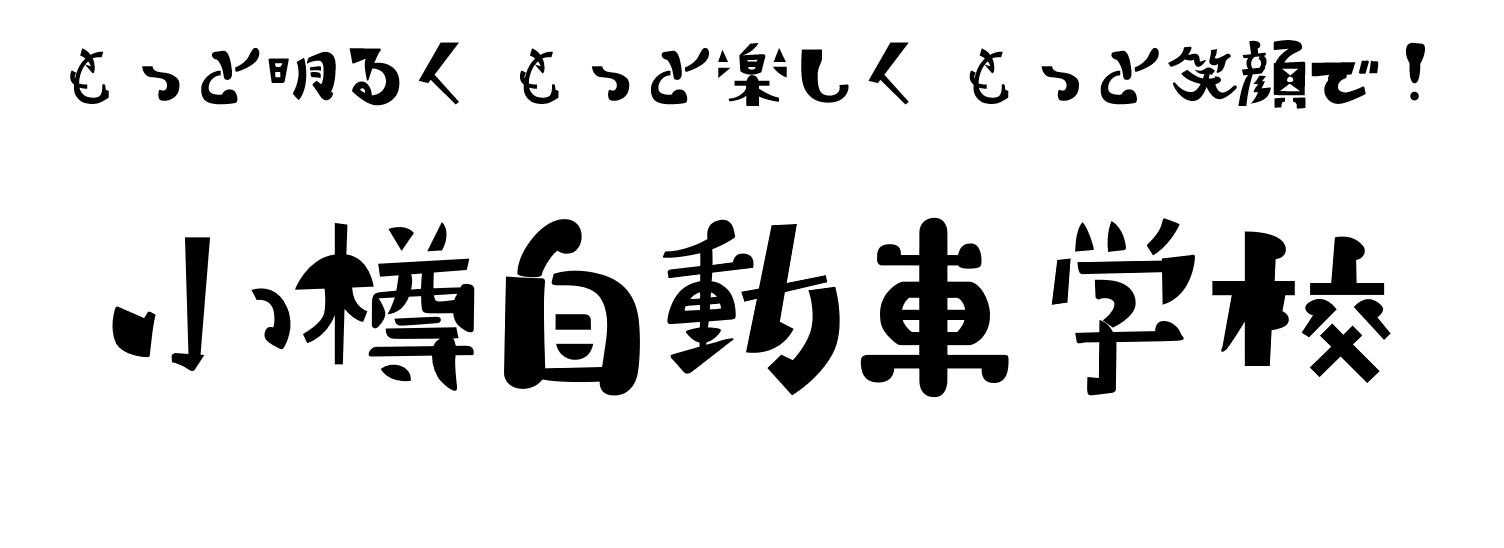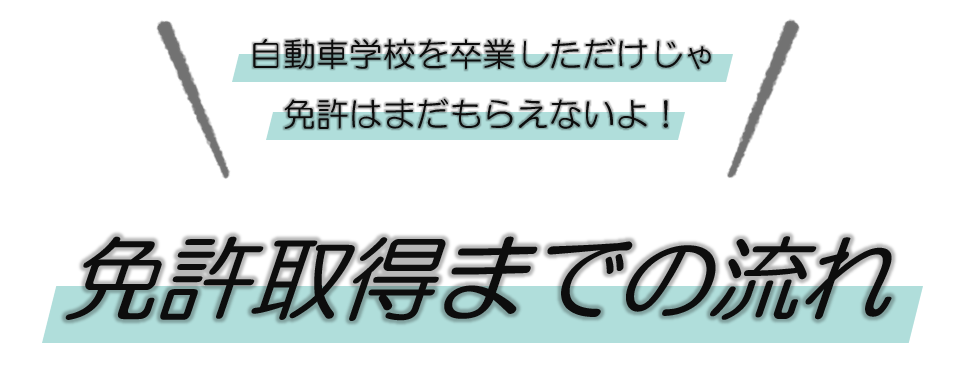
自動車学校に通い始めるところから免許を取得するところまでの流れを簡単に説明します。もっと詳しく知りたい方はメニューの「免許取得までの流れ」またはページ下の「もっと詳しく知りたい」から各段階・各出来事(教習・検定・試験など)を丁寧にそして超具体的に説明しているので参考していただけたら幸いです。

自動車学校に通い普通自動車免許の取得を検討している方に向け、入校から免許取得までの流れを大まかに説明します。

学校に到着したらまず受付で入校手続きをします。確認事項・注意事項など基本的な説明を受けたり学校のサービスの利用案内を受けたりします。そのまま受付で視力検査と(赤青黄の)色別検査を行い写真撮影を行います(卒業まで教習原簿と仮免許証の顔写真として使用されます)。その後入校説明があり、教習の流れや検定・試験等について簡単な説明を受けます。次に運転適性検査を行います。これは自分の特性(動作の正確さや素早さ、性格など)を知ったうえで教習に臨むためのものですべて筆記の検査で行われます。最後に先行学科(学科教習の第1項目)を受けます。ここでは運転免許を取得するにあたっての心構えのようなものを伝えられます。
基本的にこれで終了ですが、MT車教習生に限りトレーチャーを使った1時限目の技能教習がさらに入る可能性もあります。
入校日はこのような流れになります。後日から本格的な教習が始まります。

自動車学校では授業のことを「教習」といいます。教習には「技能教習」と「学科教習」があり、さらに第1段階と第2段階の2段階に分かれています。座学の授業を「学科教習」といい、交通規則などを学びます。実技の授業を「技能教習」といい、運転の操作などを学びます。
第1段階の技能教習は場内コースで行いますが、第2段階は路上(公道)で行うため、第1段階は路上運転(路上教習)ができるようになるための最低限の知識と技術を身につけます。そして、第2段階では状況が刻一刻と変化するなかで臨機応変に運転できるようになるための応用的な知識や技術を身につけます。
第1段階のポイントは「知識は常識に。操作は無意識に。」なるくらい体にしみこませることです。路上に出たときにはハンドルの回し方や発進・停車はできて当たり前ですし、交通ルールなどわかっていてあたりまえでなければなりません。路上には想像以上に危険が多いため、最低限の知識と技術は余裕があるくらいにしておかなければ路上で起こる不測の事態には対応できません。
第2段階のポイントは「適切な状況判断」です。路上では他の車や歩行者などがいます。教科書通りの運転はまずできません。その場の状況に合わせて適切に判断し、車を操作しなければいけません。教習中の指導員のアドバイスにしっかり耳を傾けることが大切です。

「〇〇検定」と呼ばれるものは運転の実技試験で、「〇〇試験」と呼ばれるものは運転に関する知識(交通ルール、運転の応用操作など)の筆記試験です。
路上に出て運転ができるレベルに達しているかを試すのが、第1段階の終わりにある「修了検定」と「仮免学科試験」です。修了検定と仮免学科試験に合格すれば仮免免許証が交付され、第2段階に進むことができます。そして、一人で安全に運転ができるレベルに達しているかを試すのが、第2段階の終わりにある「卒業検定」です。この時点では筆記試験はなく、自動車学校で受ける試験はこれが最後になります。卒業検定に合格すれば自動車学校は卒業することができますが、運転免許証はまだ取得できません。

卒業検定に合格すると自動車学校の卒業証明書を受け取ることができます。その卒業証明書を含め渡される書類一式を持って運転免許試験場にいくと、運転免許試験(学科試験と技能試験)を技能試験免除で受けることができます。運転免許試験の学科試験は「本免学科試験」と呼ばれており、これに合格してようやく正式な運転免許証が交付されます。